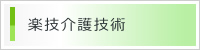1.食事のポジショニング (院内研修)
5病棟は精神科療養病棟です。毎日の生活の中でお食事は楽しみの一つですが、きちんと座れず食べにくそうにされている方や残されている方、早く食べたいと落ち着かず食事を待たれる方な ど、私たちは楽しい時間を提供できていないのではないかと反省を込めて今回患者さんとの関わり方を含めた業務改善を行い、最善最良のケア提供のために取り組んでいきます。
・今回亀山先生に研修に来ていただき、車イスで食事を食べることが姿勢に影響していることや、正しい椅子の座り方、食事前の楽しい体操など紹介して頂きました。
楽しくわかりやすい内容で今回のTQMに取り入れて楽しい食事時間を提供していきたいと思っています。
亀山先生ありがとうございました。
2.食事について(西はりま医療専門学校 作業療法学科 専任教員 亀山一義先生)
食事中の姿勢についてお話をさせていただきました。
近年、NST(Nutrition Support Team)と呼ばれる栄養サポートチームを編成し、職種の壁を越え、患者様の栄養管理に取り組む病院が増えています。
姫路北病院でも熱心に患者様の食事について様々な職種の方が取り組んでいることを感じました。
日本語の姿勢にはposition(体位)とattitude(態度)の2つの意味があります。
私はしっかりとした座位(体位)で、楽しく(態度)食事をすることが大切だと考えています。
今回のお話の中では、体位と態度について提案をさせていただきました。
この提案が病棟での食事姿勢の一助となれば幸いです。
3.研修の感想(院内研修アンケートより)
・車椅子のまま食事をすることを当然だと思い込んでいた。椅子に座って食べる事の重要さを再認識しました
・食前にストレッチを取り入れる事で、嚥下がしやすくなるという事、理解出来ました
・食事と言う行為をイベントとしてとらえる事が大切であり、そう考える事で対応が変わってくることを認識できました
・食事介助時の注意点や意識の仕方が分かりやすく、理解しやすかった。今後に活かせると思った
終了後には職員の皆様から多くの質問を頂戴し、活発な意見交換をすることができました。非常に貴重な時間となりました。ありがとうございました。